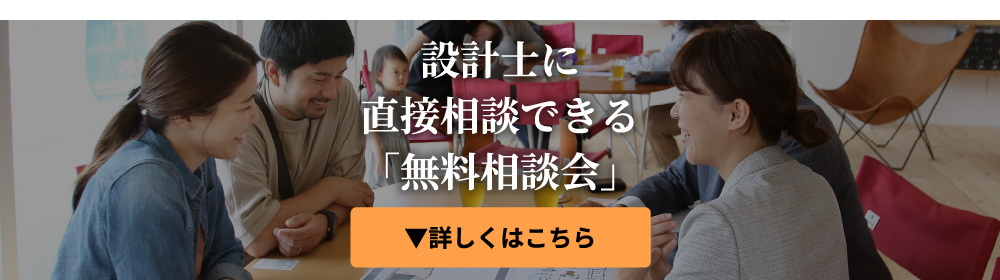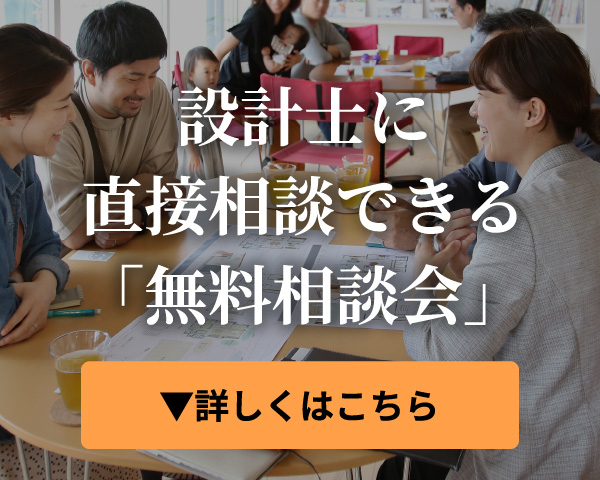土地が人をつくる ― どこに住むか ―
土地が人をつくる ― 都市と地方のあいだで ―
海に近い私の地元の朝は、潮の香りがする。
夜の湿り気を含んだ風が通り抜け、東の空がわずかに明るむ。
その匂いを吸い込むたびに、「この土地に生かされている」と感じる。
人生を変えたいなら、「住む場所」を変える。
よく聞く言葉だが、建築を生業としてきた私には、それが真理に近いと思える。
人間関係も、仕事の質も、心の状態も、結局は“どんな土地に身を置くか”で決まっていく。
朝にどんな光を浴び、どんな人とすれ違い、どんな音を聞くか。
その積み重ねが、思考と感情を少しずつ組み替えていく。
私はその“環境の力”を、数えきれない現場で見てきた。
街と田舎。どちらが正しいという話ではない。
街には「刺激と変化」があり、田舎には「静けさと持続」がある。
若い頃は前者に惹かれ、歳を重ねるほど後者に戻っていく――それは人の自然な流れだろう。
街は成長の舞台だ。多様な価値観が交差し、努力の速度を上げてくれる。
満員電車さえも、ある種のエネルギーの場になる。
競争と混沌の中で、自分の軸を磨くにはうってつけだ。
一方で田舎は、整える場所だ。
音が少なく、時間はゆっくり流れる。
風や鳥の声が、心の奥に“余白”をつくる。
その静けさが、次の挑戦への力を育ててくれる。
今のようにネットが発達した現代では、
街にいても田舎にいても、仕事の上でのハンディキャップはほとんどない。
どこにいても学び、発信し、誰かとつながることができる。
だからこそ問われるのは、「環境の質」だ。
通勤の便ではなく、思考の深さ。
情報の多さではなく、感情の静けさ。
街にいながら自然のリズムを感じる人もいれば、
田舎にいながら挑戦の風を感じる人もいる。
結局のところ、どこに住むかよりも、どんな姿勢でその土地に向き合うか。
それが、いまの時代の“住まい方”だと思う。
家づくりの打ち合わせで「どんな家を建てたいか」と尋ねると、
多くの人は間取りやデザインを語る。
しかし本当に確かめたいのは、「どんな環境の中で生きたいか」だ。
朝日が射す街か、夕暮れが美しい里か。
山の陰影に包まれるのか、街の明かりに励まされるのか。
その選択が、人生の感情の“温度”を決めていく。
街の空気で育った人と、自然の風で育った人では、
同じ言葉を話しても、心の底に流れるリズムが違う。
それが“根”となる。
家づくりとは、土地と自分の未来の“調和点”を見つけること。
朝の光の角度、風の抜け、窓の向こうの景色。
それらを整えることは、暮らしの質を整えることだ。
住まいとは、環境を設計する行為であり、人生を設計する行為でもある。
「どこに住むか」という問いは、「どう生きたいか」という問いと同じだ。
都市に住むなら何を掴むのか。地方に住むなら何を守るのか。
その見極め自体が、人生のデザインになる。
人は環境に育てられる。
だから、住む場所を選び直すことは、人生を設計し直すことに等しい。
家は暮らしを包む器であり、土地は心を育てる土壌。
人は環境に似てくる。
ゆえに――どこに住むかは、どんな人間になりたいかを決める行為である。

 092-942-2745
092-942-2745