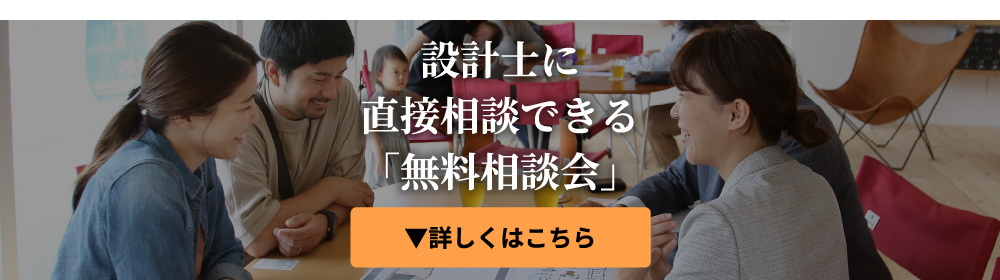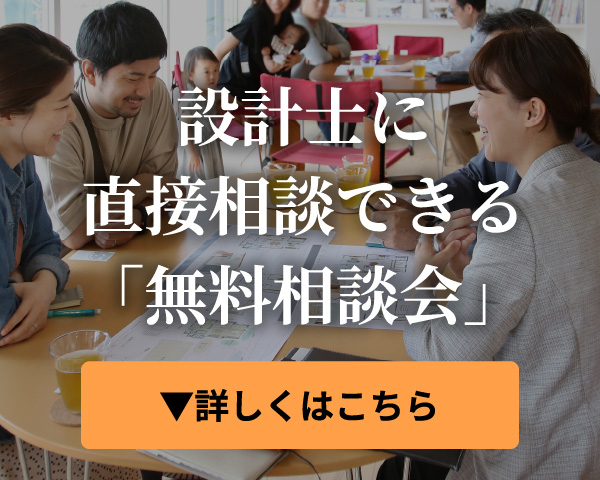仏の風が吹く場所
仏の風が吹く場所
――エアコンと和の家と、設計の苦心
今年の夏も、容赦がない。
昨日のニュースでも、量販店のエアコン工事がフル回転だという。
古い機械を外しては、新しいのを取り付けていく。
まるでタイヤ交換のように。
手際がいいのか、ただ忙しないだけなのか。
一日に何件も、立て続けに回るその姿に、悪気はないのだが
どこか「空間に冷気の出る箱を足していくだけ」という雑さを感じてしまうのは、
こちらが設計という仕事に長く関わってきたせいかもしれない。
さて、我が家の話をしよう。
一昨年、実家の改修を終えた。
築140年の和の佇まいを大切に残した家だ。
柱も、建具も、間取りも、なるべく“手を入れすぎない”ことを心がけた。
だからこそ、白い箱のようなエアコンを、ただ壁にぶら下げるわけにはいかなかった。
その“見えてしまう存在感”が、空間を壊してしまうからだ。
とはいえ、夏の暑さは年々厳しさを増す。
お盆には袈裟をつけた和尚さんがいらっしゃる。
仏間に涼しさがなければ、それはそれで失礼にあたる。
「どこでもいいから、とにかく冷房をつけてください」
嫁さんがそう言った。
静かな口調だったが、あれは本気だった。
2年目にして私は、ついに折れた。
問題は、どこに、どうやって納めるかだった。
和室は、見せていいものと、見せてはいけないものがある。
エアコンは、後者だ。
だがある日、仏壇の脇にふと目が止まった。
仏壇の余白に、ぽっかりと空いたスペースがある。
通風を妨げず、設置にも支障がない。
しかも、正面からの視線にはほとんど入らない。
「ここだ」と、直感した。
実際に設置してみると、驚くほど自然に収まった。
座って手を合わせる人のほおに、仏の風がそっと届く。
まるで蓮の池のそよ風のような、静かで、心地よい涼しさだった。
これはもう、設計者としての逆転ホームランだったと思っている。
もう一つは、縁側だ。
人目につかない南側の陽が差し込む大広間の縁側に、ひっそりと。
この位置は、以前から“暑くなる場所”として意識していた。
ただ冷やすだけでなく、“太陽光のカット”と“熱の低減”を同時に成立させる配置が必要だった。
そこに、落葉する樹木を植え、縁側に忍ばせるようにエアコンを加えた。
これもまた、実に理にかなった選択だった。
これにて、数年間続いた“嫁とのエアコン問題”にも、ついに終止符が打たれた。
設計者として、思うこと
空調機器を「見せない」ことは、単なる美意識ではない。
空間の秩序を守るという、禅的な選択でもある。
とくに古い和の空間においては、
エアコンの白い箱が見えるだけで、ノイズが気になることがある。
あの白く、人工的なラインと質感が、燻銀のような木の肌に喧嘩を売ってくるのだ。
だからこそ、風の流れだけを感じさせ、機械の存在を消す――
そのために、収まりと視線の行きどころを読むことが、
設計の仕事のひとつである。今回の処方としては仏の間に、風を隠すこととなった。
締めの一句
蓮の座に 涼しき影の 仏かな

 092-942-2745
092-942-2745