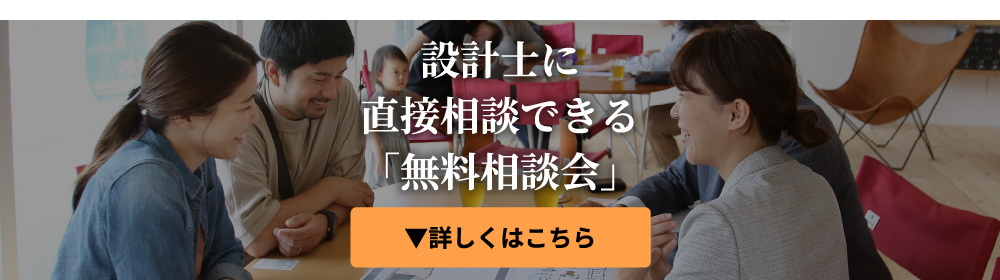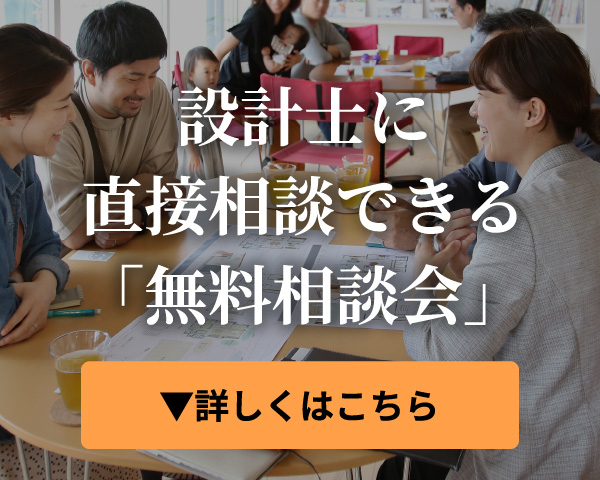風呂という場所を、もう一度考えてみた。
築20年の我が家
浴室をリニューアルすることにした。
せっかくなら、もう少し深く考えてみたくなった。
――風呂とは、なんなのだろうか。
昔の風呂やトイレには、かならず窓があった。
それは、ただ換気扇がなかったからだ。
湿気を逃がすには、窓を開けるしかなかった。
でも、いまは違う。
浴室には当たり前のように換気扇がついていて、
空気の入れ替えは機械がやってくれる。
しかも、空気の流れには“作法”がある。
浴室の入口から乾いた空気が入り、
浴槽の上をなでるように通り抜け、
天井の換気扇へと吸い込まれていく――
それが、理想的な空気の道筋だ。
ところが、窓を開けると話が変わる。
空気の流れが乱れ、湿気がこもってしまうことがある。
いわゆる「ショートサーキット」。
換気のつもりが、かえって逆効果になることもある。
それでも、人は「窓がほしい」と言う。
それはきっと、「換気」の問題ではなく、「気持ち」の問題だ。
朝、やわらかな光が射し込む風呂。
小さな窓の向こうに、空の色が見える。
閉じられた空間に、ほんの少し自然の気配があると、
それだけで、どこかほっとする。
とはいえ――
「景色が見えて、外からは見えない」なんて、
そんな都合のいい窓は、そうそう存在しない。
防犯の問題もある。
結露や掃除の手間もある。
そして多くの場合、その窓は、結局ほとんど開けられない。
夜しか風呂に入らないなら、
いっそ窓は、なくてもいいのではないか。
あるいは、「景色」ではなく「光」だけを取り込む方法はないか。
たとえば――
天井近くに、横長のFIX窓。
開閉はできないけれど、空は見える。
外の音も視線も届かず、
ただ光だけが、静かに浴室へと差し込んでくる。
それだけで、じゅうぶんかもしれない。
ふと、鏡のことも考えた。
浴室の鏡は、本当に必要だろうか。
たいていはすぐ曇り、
やがて白いウロコがこびりつき、
掃除の手間ばかりが増えていく。
身だしなみを整えるなら、洗面所でいい。
鏡はいらない。
収納棚も、カウンターも、できるだけ少なく。
そうして風呂は、だんだん「空(くう)」になっていく。
風呂とは、身体を洗う場所であり、
心を洗い流す場所でもある。
湯に身を沈め、
いらないものを、そっと手放していく。
だからこそ、余計なものはいらない。
静かで、潔くて、掃除がしやすい――
それでいい。
いまどきの風呂づくりに、
私はひとつの答えを見つけた気がする。
だから、もう「足す」のはやめようと思った。
風呂には、「引く」という美学があっていい。
それは、暮らしを“洗練”へと導く、
ひとつの所作なのかもしれない。

 092-942-2745
092-942-2745