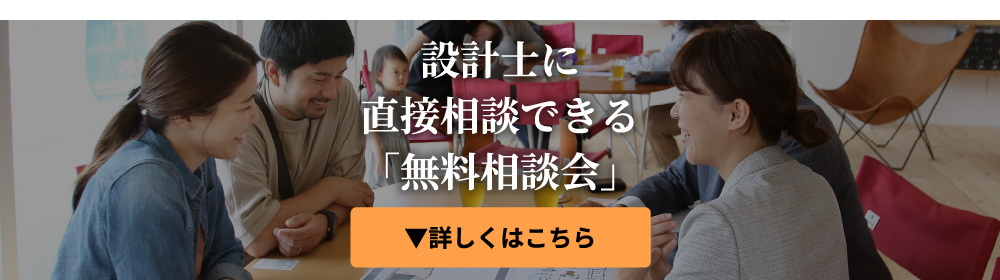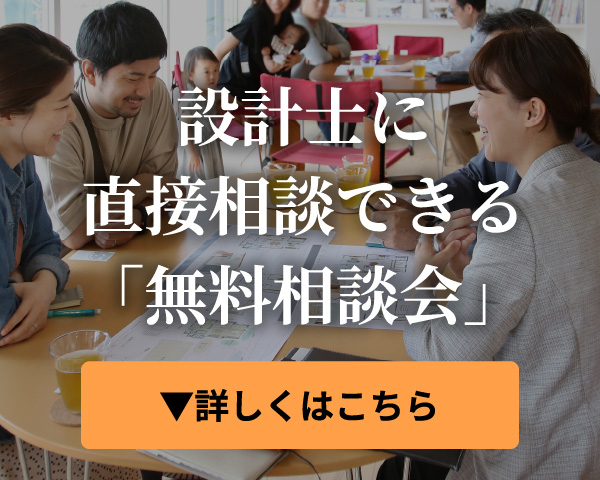捨てるということ
捨てるということ ― 空間と心の設計 ―
部屋を見れば、その人の心の状態が分かる。
捨てられないものがあるなら、それは過去に囚われている証拠。
長く建築に携わってきたが、暮らしの空間を見れば、その人の生き方が見えてくる。
散らかった部屋ほど心は乱れ、整った空間ほど人の呼吸は穏やかである。
片付けとは、ものを動かす作業ではなく、心の整理である。
人間の脳は秩序を求めるようにできている。
目に入る情報が多すぎれば、心は混乱し、判断力は鈍る。
机の上に昨日の書類が残るたび、意識の奥で小さなため息をつく。
それが積もると、気づかぬうちに“やる気”は削られていく。
私はそれを「静かな自己消耗」と呼んでいる。
整えることは、思考の再生であり、暮らしの再構築。
朝の清掃という設計
毎朝の習慣がある。
まだ街が目を覚ます前に、箒を握り家の周りを一巡する。
落ち葉を集め、砂を払う。
風の向き、土の湿り、朝の匂い。
箒を動かすたび、家の呼吸を感じる。
清掃とは、汚れを取ることではない。
自分の内側を清める行為であり、今日という日を迎えるための儀式である。
神社の朝のお祓い(はらい)のように、掃除の音は静かに空間を整えていく。
埃が消えると光が澄み、陰翳が美しく戻る。
同じ家なのに、空間が息を吹き返す。
整ったのは部屋ではなく、自分の心。
設計も同じである。
整えるとは、線を揃えることではない。
余計なためらいを捨て、“流れ”を整えること。
風の通り、光の筋、人の動き、そして心の動線。
そのすべてが自然に連なったとき、空間は初めて美しく呼吸する。
禅寺の庭が教えること
京都の禅寺の庭を歩くたび、「整える」という言葉の本当の意味を思い知らされる。
龍安寺の石庭。
十五の石が置かれただけの、静寂の庭。
そこには何もないようで、すべてがある。
砂に描かれた一本の線、石の角度のわずかな違い――
それが全体の調和を決めている。
庭師は石を動かさない。だが、砂の線は毎朝引き直す。
昨日の線は、今日の風と心には響かないから。
整えるとは、止めることではない。
絶えず変化する中で、調和を保ち続けること。
それは、空間を整える者の姿勢でもある。
建築とは、形をつくることではなく、流れと静けさをつくること。
禅寺の庭が千年の風に耐えてなお美しいのは、
その中に“人の手”と“心の静けさ”があるからであろう。
余白の美と流れの設計
日本の建築は、余白の文化である。
床の間、縁側、障子の陰――
何も置かない空間にこそ、光が宿り、風が舞う。
現代の家は、便利さの名のもとに様々なものを詰め込みすぎている。
収納を満たし、壁を飾り、情報で埋め尽くす。
だが、本当の豊かさとは、“何もないこと”を恐れない強さだと思う。
余白とは、空虚ではなく“受け入れる力”である。
建築においても、人の生き方においても、
足し算よりも引き算の方が難しい。
引く勇気、捨てる覚悟、残す判断。
それらの積み重ねが、空間の品格をつくる。
本当に美しい家は、何を加えたかではなく、
何を手放したかで決まる。
整えるという祈り
設計に関わる者として思う。
整った空間は、美しい以前に“やさしい”。
そこに住む人の呼吸を受け止め、暮らしの時間を静かに支える。
だからこそ、家は“心の器”でなければならない。
部屋を整え、心を整え、朝を整える。
それができる人は、暮らしの中に一本の軸を持っている。
建築とは、その軸をそっと支える仕事。
禅寺の庭を掃く僧のように、
余計なためらいを捨て、図面を整え、心を整え、空間を整えていく。
捨てるとは、祈りのようなもの。
繰り返し、磨き続け、やがて自分自身が整っていく。
家とは、ただ住むための場所ではない。
心を映し、静けさを取り戻すための“場所”である。
私はそう信じている。

 092-942-2745
092-942-2745