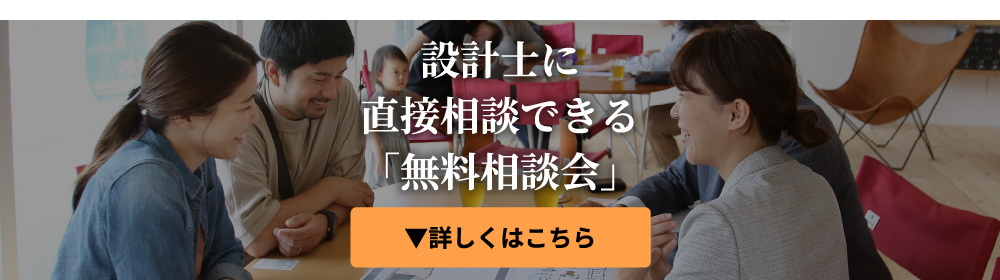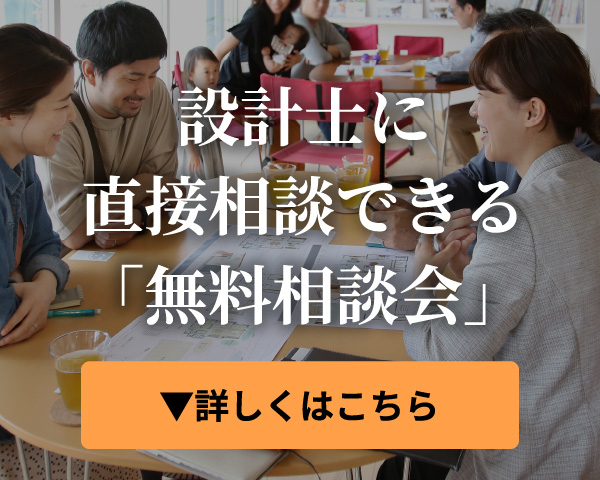秋分の日 9月23日
今年の秋分の日は 9月23日 この日の前後は太陽は真東に出て真西に沈む。
秋分の日に彼岸が行われるのは、仏教で極楽浄土が「西」にあるとされ、
「現世(此岸)」と「極楽浄土(彼岸)」が最も通じやすくなると考えられたためである。
この日を中日として前後7日間が彼岸となり、ご先祖様を供養する日とされている。
さて今日の本題。 残暑の日差しと、軒の意味。
福岡の空を見上げれば、季節ごとに太陽の高さが変わっていく。
夏至の日には南中高度が80度を超え、ほとんど真上に太陽がのぼる。
春分と秋分は57度、
冬至には33度あまり。
ひとつの町に暮らしていても、同じ空の太陽が、季節によってまったく違う角度から家を照らす。
その違いを肌で感じるのが、まさにいまの時期。
秋分を前にした残暑の光は、夏の真上から降りそそぐ光とは質が変わっている。
真夏とくらべ南中高度が55度と低くなった分、斜めから真っ直ぐに部屋の中へと差し込んでくる。
午前も午後も、家の奥まで光がのび、床や壁を照らす。
表情は柔らかく見えても、紫外線は肌に刺す。
ところが、最近は「軒のない家」が増えた。
四角い箱のような外観を選ぶ人もいる。雑誌に並ぶ写真はたしかにすっきりとして美しい。
だが、雨をしのぐにも、残暑の光をいなすにも、軒は本来欠かせぬものだ。
梅雨には雨を受け流し、初秋には日差しを和らげ、冬には程よく光を招き入れる。
数十センチの出があるだけで、暮らしの居心地はずいぶん変わる。
日本の家は、そもそも「四季の変化」に応じて形を整えてきた。
深い軒は、夏の鋭い日差しを遮り、冬の低い陽を招き入れる。
雨が多い気候には庇(ひさし)が必然であり、湿気と向き合うために縁側や風の通り道が工夫された。
先人たちは現実に合わせ、無駄のない理にかなった形を編み出してきたのだ。
それを削り、ただの「箱」としてしまったとき、家は季節に翻弄される。
残暑には眩しさと紫外線が容赦なく差し込み、雨の日は玄関が濡れ、
ゲリラ豪雨が頻発する現代においては、もはや必須ともいえる。
便利さや見た目だけで選んだ結果、最も身近な自然――陽と雨と風――に耐えられない家になる。
家は、人を守るための場所である。
流行のデザインに惑わされることなく、四季の移ろいに耐え、寄り添う工夫を持たせること。
それが「人生に耐える家」をつくる第一歩だと思う。
軒を出すという、ごく当たり前のこと。
だがその小さな工夫が、暮らしにどれほど大きな安心をもたらすか。
残暑の日差しが室内に鋭く入り込むこの時期こそ、その意味を思い返してみたい。
PS この時期、日避けとしての落葉樹樹を植えるのはおすすめの裏技である。

 092-942-2745
092-942-2745