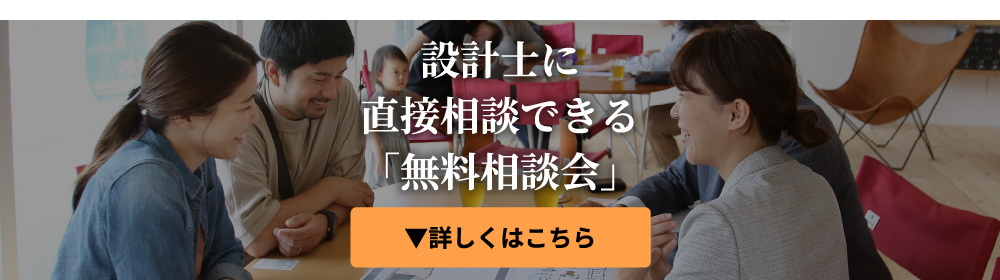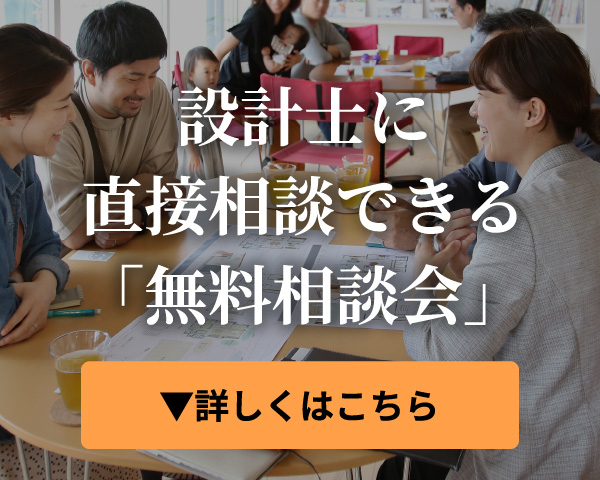時代の移ろい
昨晩、娘婿と博多で水炊きを囲んだ。
水炊きには、やはりキャベツ。これが地元の流儀である。
子どもの頃、冬になると食卓によく登場したが、あの頃は正直あまり好きではなかった。
「また水炊きか」と思ったものだ。
だが大人になってみると、この料理の奥ゆかしさが分かる。
出汁の白濁は鶏の骨の旨味であり、滋味が体に染みてくる。
それは、派手ではないが、確かに“福岡の冬”を象徴する味である。
ふと、「家で水炊きを食べたことがあるか?」と聞いてみた。
「ないです」と言う。一応福岡出身。
居酒屋でも、いまは水炊きよりももつ鍋が主流らしい。
思えば、もつ鍋がメジャーになったのは1980年代。
それ以前、福岡の鍋といえば水炊きだった。
時代は流れ、酒も変わった。
今の若い世代に「何を飲む?」と聞けば、返ってくるのは生ビールとハイボール。
会社の宴会を見ても、50歳以上はビールに焼酎の水割りやロック。
不思議なことに、ちょうど50歳を境に“焼酎文化”がぷつりと途切れている。
1990年から2000年くらいに焼酎ブームがあり、当時20〜30代だった世代が今の50~60歳。
その後、2010年代にはウイスキーのリバイバルが起こり、
2020年代にはハイボールが完全に若者の定番となった。
そして2022年、コロナによる外出自粛が“最後のとどめ”を刺したのかもしれない。
私自身もコロナの終わりに、酒を卒業した。
コロナ禍は、人との距離を物理的にだけでなく、文化的にも遠ざけた。
お酌の文化が消え、宴席の作法も変わった。
ハラスメントという言葉が、酒席の親しさにブレーキをかけた。
結果として、五合瓶と水割りセットを脇に置き、
ひとり静かに焼酎グラスを傾ける“親父”の姿だけが残った。
そういえば、最近の宴会で焼酎の瓶を見ることが少なくなった。
あの黒霧島や白波のラベルが、懐かしい時代の記憶になりつつある。
雲海のでっかいグラスあったなー
コロナを遠因とする、酒文化の世代間断絶。
それは単に嗜好の違いではなく、
人と人との「間合い」の失われた証のようにも思える。
水炊きを囲んで娘婿と語り合いながら、
鍋の湯気の向こうに、そんな時代の移ろいを見た夜だった。

 092-942-2745
092-942-2745